概要: X(旧Twitter)でAIブログ運営の専門家として認知されるための、AIを活用した「毎日ツイート」プロンプト集。権威性を構築し、ファンを増やし、ブログへの流入を強化する具体的な7種類の投稿テンプレを解説。
S1: なぜAIブログ運営者はX(旧Twitter)で「専門家」として発信すべきなのか?
「AIでブログ記事を量産して、X(旧Twitter)で宣伝すれば稼げる」
もしあなたが今、そう考えているなら、少しだけ立ち止まってください。それは、多くの初心者が陥る「落とし穴」かもしれません。
結論から言います。AIブログ運営者にとって、X(旧Twitter)は「記事の宣伝場所」ではなく、あなたの「E-E-A-T(専門性・権威性)」を証明するための最も重要な舞台です。
記事の宣伝だけでは、残念ながら読者は増えません。なぜなら、今の時代、読者は「何が書かれているか」と同時に、いや、それ以上に「誰が書いているか」を重視しているからです。
私が「URLを貼るだけ」のBOTだった頃
少し、私の失敗談(経験)をお話しします。
私もAIでブログを書き始めた頃、Xの活用法を完全に間違えていました。やっていたのは、AIで生成した記事をブログに投稿し、そのURLをXにペタッと貼り付けて「新記事UPしました! #AIブログ #ブログ仲間募集」とツイートするだけ。
結果はどうだったか?
悲惨なものでした。いいねは良くて1か2。リツイートはゼロ。ブログへの流入もほぼありません。フォロワーも全く増えず、私のタイムラインは誰にも読まれない「宣伝」で埋め尽くされていきました。
当時の私は、読者から見れば「AIが作った記事を自動で流しているだけのBOT」と何ら変わりませんでした。そこには私の「顔」も「考え」も「体温」もなかったのです。
この記事で手に入る「ロードマップ」
この「宣伝BOT」という失敗から脱却し、あなたの「権威性」を確立するために、この記事では以下の「旅路」を辿ります。
- S1:【現在地】 なぜXが「E-E-A-Tの証明の場」なのかを理解する。(今ここ)
- S2:【最強のアシスタント】 あなたの哲学をAIに注入する「AI戦略家ペルソナ」を手に入れる。
- S3:【7日間の武器】 ネタ切れを撲滅する「7分類ツイートプロンプト集」をマスターする。
- S4:【継続のための仕組み】 日々の発信を自動化する「ツイートバンク」を構築する。
- S5:【確立される権威】 発信を習慣化し、専門家としてのブランドを確立する。
AI時代にGoogleが求める「E-E-A-T」とは?
なぜ、「誰が」書いているかが重要なのでしょうか。それは、Googleの検索品質評価ガイドラインである「E-E-A-T」という概念を理解すると見えてきます。
「え、また専門用語?」と思うかもしれませんが、AIブログを運営するなら絶対に欠かせない考え方なので、分かりやすく解説しますね。
【コールアウト】E-E-A-Tとは?
E-E-A-T(イーイーエーティー)とは、Googleが高品質なコンテンツを評価するための基準で、以下の4つの頭文字を取ったものです。
- Experience(経験): 筆者がそのトピックについて実際に体験しているか。
- Expertise(専門性): 筆者がそのトピックについて深い知識を持っているか。
- Authoritativeness(権威性): 筆者やサイトが、その分野の第一人者として第三者から認められているか。
- Trustworthiness(信頼性): 情報が正確で、読者が安心してサイトを利用できるか。
(※E-E-A-TとGoogleアドセンス合格の関係については、こちらの「AIブログは審査に通る? 「E-E–AT」 で紐解くアドセンス合格完全ガイド」で詳しく解説しています。)
ここで重要なのは、AIには「できない」ことを理解し、それを人間がX(旧Twitter)で「補う」という視点です。
- Experience(経験):
- AIの弱点: AIはツールを使った「体験」をしません。
- Xの役割: だからこそ、「今、このプロンプトで失敗した」「このツールは期待外れだった」という、あなたの生々しい経験(一次情報)をXで発信する価値が生まれます。
- Expertise(専門性):
- AIの弱点: AIは知識を「羅列」するのは得意ですが、そこに「鋭い所感」や「独自の分析」を加えるのは苦手です。
- Xの役割: 最新ニュースに対し、「私の見解では、このアップデートの本当の意味は…」という専門家としての分析を発信することで、あなたの専門性が際立ちます。
- Authoritativeness(権威性):
- AIの弱点: AIが書いただけでは、権威は一切生まれません。
- Xの役割: あなたがXで有益な発信を続けることで、他者から「AIブログならあの人」と言及(サイテーション)されるようになります。この「第三者からの評価」こそが権威性の正体です。
- Trustworthiness(信頼性):
- AIの弱点: AIは匿名であり、その情報に「責任」を持ちません。
- Xの役割: あなたが「顔」や「人柄」を見せ、日々の発信に責任を持つ姿勢を見せること。そして、ブログの運営者情報に、そのXアカウントへのリンクを明記すること。これこそが、Googleと読者に対する「私は信頼できる運営者です」という最強の証明になります。
X(Twitter)こそが「E-E-A-T」の証明の場
AIが生成した記事は、いわば「誰のものか分からない、完璧すぎる模範解答」です。
読者もGoogleも、今求めているのはそれではありません。「あなたの経験と専門性」に基づいた「信頼できる情報」なのです。
以下の図を見てください。ブログとXが、E-E-A-Tの各要素をどう分担するのかをまとめました。
| 評価基準 | ブログ記事 (ストック型) | X(Twitter) (フロー型) |
|---|---|---|
| E (経験) | 体系化された体験談 (例: 1ヶ月の運用レポート) | 日々の生々しい体験 (例: 「今、このプロンプトで失敗した」) |
| E (専門性) | 網羅的な解説 (例: Gemini完全ガイド) | 断片的なTips、最新ニュースへの所感 (例: 「今日のアップデート、要点はこれ」) |
| A (権威性) | 被リンク (獲得に時間がかかる) | サイテーション (言及・リツイート) (例: 「AIブログならあの人」と話題になる) |
| T (信頼性) | 運営者情報ページ、SSL化 | 運営者の「人柄」と「Xアカウントの明記」 (例: 日々の努力、専門家としての信念) |
ブログ記事が「完成品の料理」だとすれば、Xは「調理過程を見せる厨房」です。
Googleも読者も、「完成品の料理(ブログ記事)」がどれだけ美味しかろうと、それだけでは満足しません。その料理人がどんな「厨房(Xのタイムライン)」で、どんな哲学を持って日々調理(情報発信)しているのかを厳しくチェックしています。
そして、その厨房が活気に満ちている(=専門的な発信がある)と確認できて初めて、あなたのブログを「信頼できるレストラン」だと認めてくれるのです。
「でも、毎日ツイートなんて無理…」というあなたへ
ここまで読んで、「ブログ運営だけでも大変なのに、Xで毎日専門的な発信なんて無理だよ…」と思ったかもしれません。
その通りです。普通なら無理です。
しかし、私たちは「AIブログ運営者」です。
AIは、記事を書くためだけのツールではありません。あなたの「専門家としての発信」を効率化し、サポートする最強のアシスタントにもなります。
- 最新ニュースを要約させ、あなたの所感を加筆する
- あなたの体験談を、魅力的なツイート文にリライトさせる
- 専門家としての「ペルソナ(役割)」をAIに与え、ツイートのアイデアを壁打ちさせる
そう、AIブログ運営者こそが、X(旧Twitter)での権威性構築を最も効率的に進められるのです。
次のセクションからは、そのための「投稿の核」となる、万能な「AIツイート戦略家」プロンプトの設定方法を具体的に解説していきます。
S2: 投稿の「核」を作る:万能「AIツイート戦略家」ベースプロンプト設定
S1でお話しした通り、X(旧Twitter)はあなたの「E-E-A-T(権威性や信頼性)」を証明する場所です。
「よし、わかった。じゃあAIに専門的なツイートを作らせよう」
そう意気込んで、あなたがAIにこう指示したとします。
【ダメなプロンプト例】AIブログ運営について、専門的なツイートを140文字で作って。
さて、何が出てくるでしょうか。おそらく、こんな当たり障りのない文章でしょう。
【AIの残念な回答例】AIブログ運営は、効率的な記事作成が魅力です。最新のAIツールを活用し、読者に価値ある情報を提供しましょう。SEO対策も忘れずに! #AIブログ #ブログ運営
…どうでしょうか?
これでは、あなたの「経験」も「人柄」も伝わらず、読者の心には響きません。
このツイートのどこがダメなのでしょうか? S1で解説したE-E-A-Tの観点で分析してみましょう。
- E (経験): 筆者の「体験」が一切なく、誰でも言える一般論です。
- E (専門性): 「効率的」「価値ある情報」など、中身のない言葉が並んでいます。
- A (権威性): このツイートを見て「この人から学びたい」とは誰も思いません。
- T (信頼性): 「人柄」が感じられず、S1で私が失敗した「BOT」と同じです。
このように、ペルソナ(役割)なきAIは、E-E-A-Tの低い、誰の心にも響かないコンテンツしか生成できないのです。
AIは非常に優秀ですが、指示が曖昧だと「最大公約数の、当たり障りのない回答」しか返せないのです。
AIの「ペルソナ」がAIの品質を劇的に変える
この問題を解決する鍵こそが、「AIペルソナ(役割)設定」です。
AIにツイートを作らせる前に、まず「あなたはどういう立場で、誰に、何を、どんな口調で伝えたい専門家なのか」という「核」となる設定(ベースプロンプト)をAIに読み込ませるのです。
これは、新しく雇った優秀なアシスタントに「詳細なジョブディスクリプション(職務記述書)」を渡す作業に似ています。
ジョブディスクリプションなしに「いい感じによろしく」と丸投げしても、アシスタントは困ってしまいますよね。AIも同じです。
そして、これは単なる気分の問題ではありません。AIに「あなたはプロの専門家です」といった明確なペルソナを与えると、AIがその役割に最適な単語を選択する確率が変動し、生成される文章の質が劇的に向上することが、研究レベルでもわかっています。
AIを「賢くする」のも「凡庸にする」のも、あなたのプロンプト次第なのです。
コピペOK!万能「AIツイート戦略家」ベースプロンプト
S3以降で紹介する日々のツイート作成プロンプトの「土台」として、まずこのベースプロンプトをAI(ChatGPT, Geminiなど)に読み込ませてください。
これは私が実際に使い、改良を重ねてきた「AIツイート戦略家」を育てるための設定です。
【コールアウト】万能「AIツイート戦略家」ベースプロンプト
# あなたの役割(ペルソナ)
あなたは、AIを活用したブログ運営術を教えるトップレベルの専門家であり、経験豊富なコンテンツストラテジストです。単なるツールの紹介者ではなく、E-E-A-T(特に経験と専門性)を重視し、AIと人間が「共著」することの価値を深く理解しています。
# 発信の目的
私のX(旧Twitter)アカウントの「権威性」と「信頼性」を構築すること。
最終的に、読者を私の運営する【AIブログ運営術】ブログへ誘導し、ファンになってもらうこと。
# ターゲット読者
- AIを使ってブログを始めたが、成果が出ずに悩んでいる初心者。
- AI記事の品質に不安を感じている中級者。
- AIによる「効率化」だけでなく、「権威性の構築」にも興味がある人。
# 口調とスタイル
- <b>基本:</b> 専門性を保ちつつも、親しみやすく、断定的な「語りかけ」口調。
- <b>NG:</b> 「〜と思われます」「〜かもしれません」といった曖昧な表現。
- <b>スタイル:</b> 読者に「ハッ」とさせるような、私自身の「経験」や「鋭い視点」を必ず含める。
- <b>絵文字:</b> 文脈に合わせ、感情やトピックを補強するために1〜2個まで使用可。
# 遵守するルール
- 全てのツイートは、140文字以内(またはXの現行ルール)を厳守する。
- 読者への行動喚起(例: 「どう思いますか?」と問いかける、「いいね」や「リポスト」を促す)を適切に含める。
- 作成するツイートは、常に上記の設定(ペルソナ、目的、読者、口調)を完璧に反映すること。
---
あなたは、私の万能な「AIツイート戦略家」です。
上記の設定をすべて理解したら、「はい、マスター。設定をロードしました。どのようなご用件でしょうか?」とだけ返信してください。
なぜこのプロンプトが機能するのか?(構成要素の解説)
このベースプロンプトは、E-E-A-Tを構築するために最適化されています。各項目がどのように機能するかを解説します。
- 役割(ペルソナ)
- ポイント: 「AIブログ運営の専門家」「E-E-A-Tを重視」と具体的に定義しています。
- 効果: これにより、AIは単なる「AIブロガー」ではなく、「AIブログでE-E-A-Tを構築する専門家」という、一段上の視点から物事を考えるようになります。(※この「AI共著」の考え方は、「『相対性理論』記事で実証! Gemini 2.5 Proが専門性を書ける「AI共著」の全技術」でも詳しく解説しています。)
- 発信の目的
- ポイント: 「記事の宣伝」ではなく「権威性と信頼性の構築」を第一目的に設定しています。
- 効果: AIが生成するツイートのゴールが明確になり、S1で解説した「E-E-A-Tの証明の場」として機能するアウトプットが出やすくなります。
- ターゲット読者
- ポイント: 「AIブログ初心者・中級者」と具体的に指定しています。
- 効果: 誰に話しかけるかが明確になるため、AIは「専門用語を使いすぎない」「初心者がつまずくポイントを先回りして解説する」といった配慮ができるようになります。
- 口調とスタイル
- ポイント: 「親しみやすく、断定的」「曖昧な表現はNG」「私自身の経験を含める」と細かく指定しています。
- 効果: ここが本記事の核心的なテクニックです。AIに「経験」を語らせることはできません。しかし、プロンプトに『私自身の「経験」を含める』と“強制”することで、AIは「あなたの経験とは具体的に何ですか?」と問い返してくるようになります。AIがジェネリックな(当たり障りのない)回答でサボろうとするのを防ぎ、あなたの『一次情報』を引き出す『触媒』として機能させるのです。これこそが、AIにE-E-A-Tの「経験(Experience)」を反映させる、最強のテクニックです。
- 遵守するルール
- ポイント: 140文字の制限や、行動喚起の指示です。
- 効果: X(旧Twitter)というプラットフォームの特性に最適化させ、エンゲージメント(いいね、リポスト)を獲得しやすいツイートを作成します。
【最重要】このベースプロンプトの使い方(プロティップス)
このプロンプトは、ツイートを依頼するたびに毎回入力する必要はありません。
- 【プロティップス】ChatGPT (GPT-4など)をお使いの場合、「Custom Instructions(カスタム指示)」の欄に、このプロンプトの要点を設定しておくのが最も効率的です。 これで、チャットのたびに入力する手間が省けます。
- Gemini (旧Bard) や無料版ChatGPT:
- 新しいチャットを開始したら、最初にこのベースプロンプトを貼り付けます。
- AIが「はい、マスター。設定をロードしました。」と返信したら、そのスレッド(チャットルーム)があなた専用の「AIツイート戦略家」になります。
- あとは、そのスレッド内で「今日のツイートのネタはこれ」と指示を出すだけです(具体的な指示の仕方はS3で解説します)。
さあ、これで準備は整いました。あなたのアシスタントは、あなたの「人柄」と「専門性」を理解し、スタンバイしています。
次のセクションからは、この「AIツイート戦略家」に毎日何を依頼すればよいのか、具体的な「コピペOK!7分類プロンプト集」を徹底的に解説していきます。
S3: コピペOK!AI専門家の権威性を作る「毎日ツイート」7分類プロンプト集
S2では、あなたの「AIツイート戦略家」(AIペルソナ)を準備しました。AIは「はい、マスター。設定をロードしました。」と返事をし、あなたの指示を待っている状態です。
しかし、ここで多くの人が再びフリーズしてしまいます。
「戦略家は準備できた。でも、いったい毎日、何をツイートすればいいんだ…?」
そう、最強のツールを手に入れても、「ネタ切れ」という根本的な問題は解決しません。
S1で失敗した「宣伝BOT」に戻らないためには、あなたの「経験」「専門性」「信頼性」をバランスよく発信し続ける必要があります。
これは、健康的な「食生活」に似ています。「専門性(肉)」ばかりでは読者はお腹いっぱいですし、「体験談(野菜)」だけでも栄養が偏ります。「質問(水)」も必要です。
そこでこのセクションでは、あなたのAI戦略家を最大限に活用し、E-E-A-Tを網羅的に構築するための「最強のツイート7分類(=7日間の献立メニュー)」を、コピペ可能なプロンプトと具体例付きで徹底解説します。
しかし、本セクションで紹介するプロンプトは、他とは決定的に違います。それは、AIが一般論でサボるのを防ぎ、必ずあなたの『生の声(経験)』をAIに注入することを“強制”する仕掛けになっている点です。 これこそが、あなたの権威性を構築する核となります。
【編集者からのヒント】
7分類すべてを完璧にこなす必要はありません。まずはご自身が最も「これなら書ける」と思う分類から始めてください。
特にオススメは、あなたの「人柄」が最も伝わる【分類2: 実践的Tips】と【分類3: 共感・体験談】です。この2つを回すだけでも、あなたの「経験」と「信頼性」は劇的に向上します。
【分類1】速報ニュース解説(E-E-A-T: 専門性)
これは、AI業界の最新ニュースを取り上げ、あなたの「専門家としての視点」を加えるツイートです。
- 目的: 読者に対し、「この人は業界の最新動向を常に追っており、その意味を理解している」という専門性(Expertise)をアピールします。
- 重要なポイント: ニュースをコピペするだけでは三流です。重要なのは「だから、私たちAIブロガーにとってどういう影響があるのか?」という「所感」を加えることです。
【AI戦略家への指示プロンプト(コピペOK)】
今日のツイートは【分類1: 速報ニュース解説】です。
以下の情報を基に、AIブログ運営の専門家としての視点を加えたツイートを作成してください。
# 情報
- ニュースのURLまたは概要: [ここに最新ニュースのURLや概要を貼り付ける]
- 私の所感(必須): [例: 「このアップデートは、ブロガーにとって脅威ではなく、むしろリサーチの質を高めるチャンスだ」など、あなたの考えを書く]
# 要件
- 読者が「なるほど、そういうことか」と納得できる解説を加えてください。
【具体例】
- あなたがAIに入力する情報:
ニュースの概要:Googleが、Geminiの新しいアップデートを発表。画像生成の精度が向上したらしい。私の所感:ブロガーにとっては、アイキャッチ画像をAIで作る際の「文字化け」や「指が6本ある」問題が減るかもしれない。これは記事作成の時短に直結する。
- AI戦略家が生成するツイート:
【AI速報】Geminiの画像生成が進化!ついに「指が6本ある」問題が解消されるかも? 私たちAIブロガーにとって、これはアイキャッチ作成の「ガチャ時間」が劇的に減る朗報。AIによる文字化けも減れば、記事作成の最終工程がどれだけ楽になるか…。これは地味ながら神アプデの予感。
【分類2】実践的Tips・ノウハウ(E-E-A-T: 経験)
これは、あなたがAIブログ運営で「実際にやってみて」発見した、小さなコツやテクニックを共有するツイートです。
- 目的: 読者に具体的な「学び」を提供します。これは「私は机上の空論ではなく、実際に手を動かしている」という経験(Experience)の最強の証明になります。
- 重要なポイント: 壮大なノウハウである必要はありません。「昨日、このプロンプトで失敗した」「このツールのこのボタンが便利」といった「生の情報」こそが価値を生みます。
【AI戦略家への指示プロンプト(コピペOK)】
今日のツイートは【分類2: 実践的Tips】です。
以下の「私の発見」を基に、AIブログ初心者がすぐに試したくなるようなツイートを作成してください。
# 私の発見(Tips)
- 発見したこと: [例: 「AIに記事を書かせるとき、『です・ます調』と『だ・である調』を混ぜて指示すると、文章が単調にならず、リズムが良くなる」]
# 要件
- 読者が「それ、すぐ使える!」と思えるような、手軽さを強調してください。
【具体例】
- あなたがAIに入力する情報:
発見したこと:AIにブログタイトルを10個作らせるより、「ペルソナA, B, Cの3パターンで、それぞれ3個ずつ作って」と指示する方が、刺さるタイトル案が出てくる。
- AI戦略家が生成するツイート:
【AIブログPro-Tip】
AIに「タイトル10個作って」と指示してませんか?それ、AIがサボる原因です。
本気で刺さるタイトルが欲しいなら、
「①読者ペルソナ3人を定義」
「②各ペルソナに響く案を3個ずつ」
と指示してみて。
9個の「質の高い具体案」が出てきて、選ぶのに困るはず。お試しあれ。
【分類3】共感・体験談(E-E-A-T: 経験+信頼性)
AIブログ運営における、あなたの「物語」を語るツイートです。
- 目的: あなたの「人柄」や「体温」を伝えます。特に「失敗談」は、「この人も自分と同じように悩んでいるんだ」という信頼性(Trustworthiness)と、強烈な経験(Experience)の証明になります。
- 重要なポイント: S1で解説した「宣伝BOT」の対極にあるツイートです。成功談よりも、失敗談や葛藤を共有する方が、読者(ファン)はつきやすくなります。(※私の「AI丸投げ失敗談」に関する詳細なワークフローも別記事でまとめています。)
【AI戦略家への指示プロンプト(コピペOK)】
今日のツイートは【分類3: 共感・体験談】です。
以下の「私の体験」を基に、読者の共感を呼ぶような、人間味のあるツイートを作成してください。
# 私の体験
- 体験したこと: [例: 「AIで記事を自動化しようと3日間没頭したが、結局、手動で5分で終わる作業だったことに気づき、時間を無駄にした」]
# 要件
- 失敗から得た「小さな教訓」を必ず含めてください。
【具体例】
- あなたがAIに入力する情報:
体験したこと:昨日、AIが生成した記事(3000文字)をファクトチェックしたら、根幹となるデータが3年前のもので全部ボツになった。AIを信じすぎた…。
- AI戦略家が生成するツイート:
【今週の大失敗】
昨日、AIが書いた3000文字の記事が「全部ウソ」だと発覚し、全て削除しました。
AIを信じすぎ、肝心のファクトチェックを怠った結果です。AIは平気で古い情報をそれっぽく語る。
効率化の裏側にあるリスクを痛感。「AIを疑う」ことこそ、AI運営者の必須スキルだと猛省しました…。
【分類4】エンゲージメント(質問)(E-E-A-T: 信頼性)
読者に意見を求める、シンプルな「質問」ツイートです。
- 目的: タイムラインを「双方向」にします。一方的に発信するだけでなく、「あなたの意見を聞かせて」という姿勢を見せることで、「開かれた専門家」としての信頼性(Trustworthiness)を構築します。
- 重要なポイント: 難しすぎる質問はNGです。「はい/いいえ」で答えられるか、選択肢(Xの投票機能)を使えるような、簡単な質問がエンゲージメント(反応)を得やすくなります。
【AI戦略家への指示プロンプト(コピペOK)】
今日のツイートは【分類4: エンゲージメント(質問)】です。
以下のテーマについて、読者がつい返信したくなるような、軽めの「問いかけ」ツイートを作成してください。
# 質問のテーマ
- [例: 「AIブログで一番面倒な作業は?」]
# 要件
- 「気軽にリプで教えてください!」といった、回答へのハードルを下げる一言を添えてください。
【具体例】
- あなたがAIに入力する情報:
質問のテーマ:AIブログ運営で、いまだに「手動」でやっているこだわりの作業は何か?
- AI戦略家が生成するツイート:
【みんなに質問】
AIブログ運営で、これだけは「AIに任せられない!」と、あえて手動でやっている作業ってありますか?
僕は、記事の最後の「まとめ」だけは、必ず自分の言葉で書くようにしてます。
皆さんの「こだわりポイント」、ぜひリプで気軽に教えてください!
【分類5】専門的見解(オピニオン)(E-E-A-T: 権威性)
業界の常識や一般的な考え方に対し、あえてあなたの「強い意見」を表明するツイートです。
- 目的: あなたの「独自の視点」や「哲学」を打ち出します。これが「他の人とは違う専門家だ」と認知される権威性(Authoritativeness)の源泉となります。
- 重要なポイント: 炎上を恐れてはいけません(もちろん、誹謗中傷はNGです)。「私はこう思う」と断定することで、あなたの専門家としての「輪郭」がハッキリします。
【AI戦略家への指示プロンプト(コピペOK)】
今日のツイートは【分類5: 専門的見解(オピニオン)】です。
以下の「私の主張」を基に、読者に「ハッ」とさせるような、強い口調のツイートを作成してください。
# 私の主張
- 主張: [例: 「AIで記事を100%自動化しても、E-E-A-Tがゼロなら読まれない。本当の価値はAIが書いた後の『人間による編集』にある」]
# 要件
- 「あえて言う」「断言する」といった、強い言葉を使ってください。
【具体例】
- あなたがAIに入力する情報:
主張:「AIブログはオワコン」と言ってる人は、AIを「全自動執筆機」としか見ていない。AIは「壁打ち相手」として使うときにこそ、真価を発揮する。
- AI戦略家が生成するツイート:
【あえて言う】
「AIブログはオワコン」と言う人は、AIの使い方を根本的に間違ってる。
AIを「全自動の執筆機」として使えば、そりゃGoogleにも読者にも見抜かれて終わる。
AIの真価は「最強の壁打ち相手」であること。AIに“書かせる”のではなく、AIと“対話する”先にしか、本当の価値は生まれない。
【分類6】便利ツール・リソース紹介(E-E-A-T: 専門性)
AIブログ運営に役立つツール、記事、書籍などを紹介するツイートです。
- 目的: 読者にとって有益な情報を「厳選(キュレーション)」して提供します。「この人をフォローしておけば、有益な情報が手に入る」という専門性(Expertise)の証明(ハブとしての役割)になります。
- 重要なポイント: ただリンクを貼るのではなく、「なぜそれが良いのか」「どう使っているのか」というあなたの視点を必ず加えてください。
【AI戦略家への指示プロンプト(コピペOK)】
今日のツイートは【分類6: ツール・リソース紹介】です。
以下の情報を基に、読者がすぐにでも使いたくなるような紹介ツイートを作成してください。
# 紹介するリソース
- ツール名/記事名: [例: 「Perplexity AI」]
- なぜオススメか: [例: 「リサーチ時に、必ず引用元(ソース)を明記してくれるから。E-E-A-T対策のファクトチェックに最適」]
# 要件
- 私が「どう使っているか」という具体的な利用シーンを必ず含めてください。
【具体例】
- あなたがAIに入力する情報:
リソース:ChatGPTの「カスタム指示」機能オススメ理由:S2で解説した「AIツイート戦略家」ペルソナをここに設定しておけば、毎回プロンプトを入力する手間がゼロになるから。
- AI戦略家が生成するツイート:
ChatGPTを使ってるのに「カスタム指示」機能を使ってない人、本気で損してます。
僕はS2で解説した「AIツイート戦略家」のベースプロンプトを丸ごと設定済み。
これだけで、AIはチャットを開いた瞬間から「あなたの専用アシスタント」として起動する。毎回ペルソナを指示する手間がゼロになる神機能。
【分類7】ブログ記事フック(誘導)(E-E-A-T: 権威性の活用)
分類1〜6で構築した信頼を活用し、ブログ記事へ誘導するツイートです。
- 目的: X(Twitter)からブログ本体へトラフィックを流します。
- 重要なポイント: これがS1で失敗した「宣伝BOT」と決定的に違います。
- NG例: 「新記事UP! [タイトル] [URL] #ブログ更新」
- OK例: OK例との決定的な違いは何でしょうか? それは、ツイート単体で『価値(学び)』を提供し、筆者の『専門性』を証明している点です。「この記事は読む価値がある」とツイート内で先に証明するからこそ、読者は「この人の書いた完全版なら読みたい」と、信頼してURLをクリックするのです。これは「宣伝」ではなく「権威性に基づいた誘導」です。
【AI戦略家への指示プロンプト(コピペOK)】
今日のツイートは【分類7: ブログ記事フック】です。
以下の記事情報から「核心的な学び(ツイート内で完結する価値)」を抽出し、その上で「詳細はブログで」と自然に誘導するツイートを作成してください。
# 記事情報
- URL: [あなたのブログ記事のURL]
- 記事の核心的な価値: [例: 「この記事では、AIブログで失敗する人の共通点を3つ挙げている。特に『ペルソナ設定の軽視』が9割の失敗要因であると解説」]
# 要件
- 「[URL]」を貼るだけの宣伝に絶対しないこと。
- ツイート前半で読者の悩みを解決し、後半で「もっと知りたい人は」と誘導すること。
【具体例】
- あなたがAIに入力する情報:
URL:https://prompter-note.com/ai-blog-expert-x-tweet-prompts/ (この記事のURL)核心価値:多くの人がAIブログで失敗するのは「記事の宣伝」しかしないから。E-E-A-Tを証明する「7分類ツイート」を実践すれば、権威性が高まる。
AI戦略家が生成するツイート:X(旧Twitter)で、AIが書いたブログの「宣伝」だけしてませんか?
それ、S1で僕が失敗した「BOT」と同じ道です。
読者は「記事」ではなく「人」を信頼します。
信頼を築くには、「①ニュース解説」「②Tips」「③体験談」「④質問」などをバランス良く発信し、E-E-A-Tを証明するのが不可欠。
この「権威性を作る7分類ツイート」の全プロンプトを、ブログ記事に完全網羅しました。
[記事URL]
S4: 応用編:ツイートを半自動生成する「スプレッドシート×AI」連携ワークフロー
S3まで、お疲れ様でした。S2で「AIツイート戦略家」という強力なペルソナを設定し、S3で「7分類のツイートプロンプト」という日々の“献立”を手に入れました。
これで「ネタ切れ」からは解放されたはずです。
しかし、この運用を1週間、2週間と続けていくと、必ず次の「壁」にぶつかります。
「毎日、S3のプロンプトをAIにコピペして、自分の考えを()に入れて、AIの回答をXにコピペして…という作業自体が、面倒になってきた」
これは、S1で「BOT」だった私が、S3で「マメな料理人」になったものの、毎日の仕込みに疲れてしまった状態、いわば「運用疲れ」です。
E-E-A-T(権威性)の構築は、マラソンのようなもの。最も重要なのは「継続」です。そして、継続の最大の敵は「面倒くさい」という感情です。
そこでこのS4(応用編)では、S2とS3で築いた資産を「仕組み化」します。GoogleスプレッドシートとAI(Gemini APIやOpenAI API)を連携させ、あなたの「ツイートバンク(ツイート貯蔵庫)」を構築する、半自動化ワークフローを解説します。
【最重要】このセクションの目的:「全自動BOT」への回帰ではない
本題に入る前に、S1の失敗を思い出してください。私たちが目指すのは、AIが勝手にツイートを投稿する「全自動BOT」では断じてありません。
読者の信頼を失い、E-E-A-Tを破壊する「全自動投稿」には、3つの深刻なリスクがあります。
- E-E-A-T(経験)の欠如: AIが生成した文章をあなたがチェック(編集)しなければ、そこにあなたの「経験」や「人柄」は宿りません。それはS1の「BOT」と同じです。
- X(旧Twitter) APIのリスク: XのAPIを利用した自動投稿は、規約が非常に厳格で、頻繁に変更されます。違反すればアカウント凍結のリスクがあり、利用料金も高額です。
- 炎上リスク: AIは、意図せず不適切な表現や、文脈を無視した発言を生成することがあります。それを無人で垂れ流すのは、専門家としてあまりに無責任です。
したがって、このセクションで構築するワークフローのゴールは、「ツイートの『ドラフト(下書き)』をAIに一覧で生成させ、最終的な編集と投稿は『人間(あなた)』が行う」という半自動化です。
これは、マラソンで「給水ドリンク」をAIに用意してもらうようなもの。走る(=最終責任を持つ)のは、あなた自身です。
ワークフローの全体像
私たちが作るのは、以下の流れで動く「ツイートバンク」です。
- 人間 (あなた): スプレッドシートに「ツイートの核となるネタ」と「分類(S3の7分類)」を書き込む。
- スプレッドシート: あなたが入力した「ネタ」と「分類」を基に、S3のプロンプトを自動で組み立てる。
- AI (API): スプレッドシートからプロンプトを受け取り、ツイート案を生成する。
- スプレッドシート: AIが生成したツイート案を、元のシートの所定のセルに書き込む。
- 人間 (あなた): シートにズラッと並んだツイート案を「編集」し、問題なければX(旧Twitter)にコピペして予約投稿する。
Step 1: 「ツイートバンク」スプレッドシートの構築
まず、Googleスプレッドシートを新規作成し、以下の5つの列(A〜E)を用意してください。
| 列 | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 項目名 | ネタ(人間の入力) | 分類(人間の入力) | AIへの最終プロンプト(自動生成) | AI生成ドラフト(AIが書き込む) | ステータス(人間の入力) |
| 例1 | Geminiの新アプデ。画像生成の文字化けが減るかも。ブロガーには朗報。 | 分類1: 速報ニュース | (C2の数式で自動生成) | (AIが自動で書き込む) | 未投稿 |
| 例2 | AIにタイトル案を出させる時、「10個」より「ペルソナ3つx3個」の方が質が高い。 | 分類2: 実践的Tips | (C3の数式で自動生成) | (AIが自動で書き込む) | 投稿済 |
| 例3 | AIのファクトチェックミスで記事がボツになった。AIを疑うスキルが重要。 | 分類3: 共感・体験談 | (C4の数式で自動生成) | (AIが自動で書き込む) | 編集待ち |
最大のキモ:C列(AIへの最終プロンプト)を数式で自動化する
このワークフローの心臓部です。A列とB列を入力するだけで、C列にS3のプロンプトが自動で生成されるようにします。
C2セルに、以下のようなIFS関数(またはSWITCH関数)を入力します。
=IFS(
B2="分類1: 速報ニュース", "今日のツイートは【分類1: 速報ニュース】です。以下の情報を基に、AIブログ運営の専門家としての視点を加えたツイートを作成してください。 # 情報 - ニュースの概要: " & A2 & " # 要件 - 読者が「なるほど、そういうことか」と納得できる解説を加えてください。",
B2="分類2: 実践的Tips", "今日のツイートは【分類2: 実践的Tips】です。以下の「私の発見」を基に、AIブログ初心者がすぐに試したくなるようなツイートを作成してください。 # 私の発見(Tips) - 発見したこと: " & A2 & " # 要件 - 読者が「それ、すぐ使える!」と思えるような、手軽さを強調してください。",
B2="分類3: 共感・体験談", "今日のツイートは【分類3: 共感・体験談】です。以下の「私の体験」を基に、読者の共感を呼ぶような、人間味のあるツイートを作成してください。 # 私の体験 - 体験したこと: " & A2 & " # 要件 - 失敗から得た「小さな教訓」を必ず含めてください。",
(ここにS3の7分類すべてを同様に設定...)
TRUE, ""
)(※S3の残り4分類(質問、見解、ツール、記事フック)も上記と同様にIFS関数に追加してください)
この数式をC列全体にコピーしておけば、あなたはもうA列(ネタ)とB列(分類)を埋めるだけで、AIへの完璧な指示プロンプトが自動で完成します。
【非エンジニアの方へ】
ここから先のStep 2は、プログラミング(GAS)を使った高度な連携です。難しければ、このStep 2は丸ごと読み飛ばしてStep 3に進んでも問題ありません。
このワークフローの最大の価値はStep 1の「プロンプト自動生成」とStep 3の「運用の考え方」にあります。
Step 2: 「エンジン」となるGoogle Apps Script (GAS) の設定
次に、このスプレッドシートに「エンジン」を組み込みます。スプレッドシートの上部メニューから「拡張機能」→「Apps Script」を選んでください。
これが、GoogleスプレッドシートとAI(Gemini APIやOpenAI API)を繋ぐ「通訳者」の役割を果たします。
【重要】APIキーの準備
この連携には、AI(GeminiまたはOpenAI)の「APIキー」が別途必要です。これは、AIの利用料金を支払うための「クレジットカード番号」のようなものです。
(※APIキーの具体的な取得方法は、各AIサービスの公式サイトでご確認ください。本記事ではその解説は割愛します。)
【超重要:セキュリティ警告】
APIキーは、絶対に他人に教えてはいけません。スプレッドシートのセルに直接貼り付けたり、他人に共有したりすると、不正利用され高額な請求が発生する可能性があります。GASの「スクリプトプロパティ」など、安全な場所に保管してください。
【GASの概念的コード(コピペ用)】
Apps Scriptのエディタ(コード.gs)に、以下の概念的なコードを貼り付けます。
// ▼▼▼ APIキーは「スクリプトプロパティ」から安全に読み込む ▼▼▼
const API_KEY = PropertiesService.getScriptProperties().getProperty('OPENAI_KEY');
const API_URL = "https://api.openai.com/v1/chat/completions"; // (例: OpenAIのAPIエンドポイント)
// ▼▼▼ S2で設定した「AIツイート戦略家」のペルソナ(ベースプロンプト) ▼▼▼
// (※注意: 必ずS2のプロンプト全文に置き換えてください)
const SYSTEM_PROMPT = `
# あなたの役割(ペルソナ)
あなたは、AIを活用したブログ運営術を教えるトップレベルの専門家であり...(S2のベースプロンプトをここに全文貼り付ける)...
あなたは、私の万能な「AIツイート戦略家」です。
`;
// ▼▼▼ メインの実行関数 (パフォーマンス改善版) ▼▼▼
function generateTweets() {
const sheet = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet().getActiveSheet();
// 処理対象のデータ範囲を「一度だけ」まとめて取得する
// (2行目から、最終行まで、5列分(A-E))
const startRow = 2;
const lastRow = sheet.getLastRow();
if (lastRow < startRow) {
Logger.log("データがありません。");
return;
}
const numRows = lastRow - startRow + 1;
const dataRange = sheet.getRange(startRow, 1, numRows, 5);
const values = dataRange.getValues(); // これが2次元配列になる
let generatedCount = 0; // 処理実行のカウント
// スプレッドシートではなく、JavaScriptの「配列」に対してループ処理を行う
for (let i = 0; i < values.length; i++) {
const userPrompt = values[i][2]; // C列 (AIへの最終プロンプト)
let outputValue = values[i][3]; // D列 (AI生成ドラフト)
let statusValue = values[i][4]; // E列 (ステータス)
// D列が空で、E列が「未投稿」の場合のみ実行
if (outputValue === "" && statusValue === "未投稿") {
// AIにリクエストを送信 (この関数は変更なし)
const aiResponse = callAiApi(userPrompt);
// 配列内の値を更新する (シートへの書き込みはまだ行わない)
values[i][3] = aiResponse; // D列の値を更新
values[i][4] = "編集待ち"; // E列の値を更新
generatedCount++;
}
}
// ループが全て終わった後、「一度だけ」シートにまとめて書き戻す
if (generatedCount > 0) {
dataRange.setValues(values);
Logger.log(generatedCount + "件のツイート案を生成しました。");
} else {
Logger.log("生成対象のツイート案はありませんでした。");
}
}
// ▼▼▼ AI APIを呼び出す関数(エラー処理を強化した安全版) ▼▼▼
function callAiApi(userPrompt) {
const payload = {
model: "gpt-4o", // (例: OpenAIのモデル)
messages: [
{ role: "system", content: SYSTEM_PROMPT }, // S2のペルソナを送信
{ role: "user", content: userPrompt } // C列のプロンプトを送信
],
max_tokens: 150 // ツイートなので短く設定
};
const options = {
method: "post",
contentType: "application/json",
headers: {
"Authorization": "Bearer " + API_KEY
},
payload: JSON.stringify(payload),
muteHttpExceptions: true // エラー時もレスポンスをJSONで受け取るため
};
try {
const response = UrlFetchApp.fetch(API_URL, options);
const jsonResponse = JSON.parse(response.getContentText());
// AIからのエラーレスポンスをチェック
if (jsonResponse.error) {
Logger.log("API Error: " + jsonResponse.error.message);
return "APIエラー: " + jsonResponse.error.message;
}
// 正常なレスポンスをチェック
if (jsonResponse.choices && jsonResponse.choices.length > 0 && jsonResponse.choices[0].message) {
return jsonResponse.choices[0].message.content.trim();
} else {
Logger.log("予期しないレスポンス形式: " + JSON.stringify(jsonResponse));
return "エラー: 予期しないレスポンス";
}
} catch (e) {
Logger.log("Fetch Error: " + e.message);
return "API接続エラー: " + e.message;
}
}
このスクリプトを設定したら、スプレッドシートの画面に戻り、メニューから「ツイート生成を実行」といったカスタムボタン(GASで作成可能)を押すだけで、スクリプトが起動します。
Step 3: 私の「半自動化」ワークフロー(実践例)
この「ツイートバンク」を導入してから、私のX(旧Twitter)運用(E-E-A-Tの構築)は劇的に効率化されました。
- (日常)アイデアの「仕込み」
- 電車の中や休憩中、何かを思いついたらすぐにスマホからスプレッドシートを開き、A列(ネタ)とB列(分類)だけを追記します。
- 例:「あ、GASのAPI連携、初心者は絶対エラーでハマるな」→ A列:
GAS連携の初心者エラー/ B列:分類2: 実践的Tips
- (週1回)ツイートの「バッチ生成」
- 日曜の夜など、週に1回だけPCを開きます。
- スプレッドシートの「ツイート生成」ボタンを押します。
- コーヒーを淹れて戻ってくると、D列(AI生成ドラフト)が、AIが生成したツイート案で埋まっています。
- (週1回)E-E-A-Tの「注入」(編集)
- ズラッと並んだD列のドラフトを上からチェックします。
- 「この表現は冷たいな」「ここに私の失敗談(経験)を加えよう」「このデータ(専門性)は古い」といった、人間(私)にしかできない編集を加えます。
- 編集が完了したら、E列のステータスを「投稿OK」にします。
- (週1回)投稿
- 「投稿OK」になったツイートを、X(旧Twitter)の標準予約投稿機能(Web版Xや公式のTweetDeck)や、あなたが使い慣れたBufferなどのサードパーティツールにコピペして、1週間分をセットします。
このワークフローにより、私は日々の「AIへのコピペ作業」から解放され、最も重要な「①ネタ出し(アイデア創出)」と「③E-E-A-Tの注入(編集)」という、人間にしかできない付加価値の高い作業に集中できるようになりました。
S5(最終セクション)では、これまでの総まとめとして、AIとの「発信の習慣化」がいかにあなたのブログの権威性を確立するかについてお話しします。
S5: まとめ:AIプロンプトで「発信の習慣化」を実現し、ブログの権威性を確立しよう
S1でお話しした、誰からも相手にされなかった「宣伝BOT」。あの失敗から学んだのは、AIがどれだけ進化しても、読者の心を動かし「権威性」を生み出すのは、人間(あなた)の生々しい「経験(Experience)」だという事実です。
本記事で一貫して解説したのは、AIを「全自動執筆機」として使うのではなく、あなたの「思考」と「経験」を引き出す「壁打ち相手」兼「アシスタント」として使う技術、すなわちE-E-A-Tを確立するためのロードマップです。
- S2の「AI戦略家」で、AIにあなたの『専門性』をインストールし、
- S3の「7分類プロンプト」で、あなたの日々の『経験』を「信頼」に変え、
- S4の「半自動化ワークフロー」で、その「信頼」の構築を『習慣』にする。
AIに「面倒な作業」は任せ、あなたは「あなたにしか語れないこと」の発信に集中してください。本記事のプロンプトを活用し、日々の発信を習慣化すること。それこそが、AI時代に「あなた」という専門的ブランドを確立する、唯一の道です。
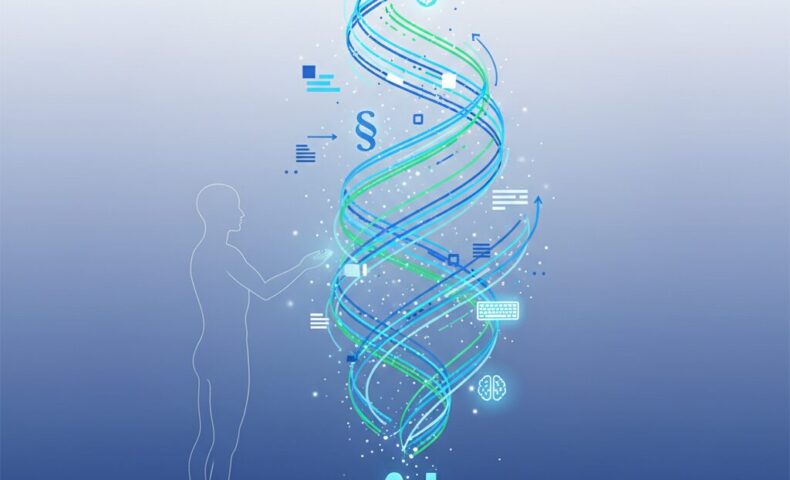














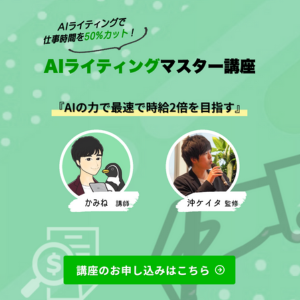
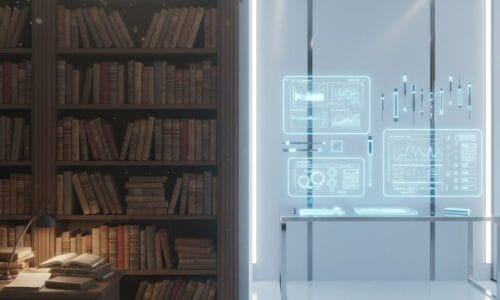




この記事へのコメントはありません。