導入:なぜ今、AIブログに「炎上回避術」が必要なのか?
「AIで記事を自動生成すれば、寝ている間にもブログが育っていく」…そんな夢のような話が現実になりました。AIの進化は凄まじく、私自身、日々のブログ運営でAIの助けを借りない日はありません。
しかし、AIに任せた記事草案をチェックした際、他サイトの記事と酷似した表現(デッドコピー)が紛れ込んでいて、公開前に冷や汗をかいた経験も一度や二度ではありません。
この「便利さ」や「効率化」という側面にだけ目を奪われ、無防備にAIに「丸投げ」してしまった結果、取り返しのつかない事態に陥るブロガーが後を絶ちません。
それが、「炎上」リスクです。(SNSで批判が殺到するだけでなく、Googleから「E-E-A-Tに欠ける低品質なサイト」と判断され、検索順位が圏外に飛ぶといった、運営者にとって致命的な事態を招きかねません)
AIブログ運営には、あなたが気づかぬうちに忍び寄る、大きく分けて2つの「時限爆弾」が潜んでいます。
1. 「知らなかった」では済まされない「著作権侵害」
AIは、インターネット上の膨大なテキストデータを学習して文章を生成します。その過程で、AIが学習した他人のブログ記事やニュース記事と酷似した表現を、意図せず生成してしまう可能性があります。
もし、あなたがAIの出力をそのままコピペして公開し、それが他者の著作権を侵害していたら?
法的な責任を問われるのは、AIではなく、記事を公開した「あなた自身」です。「AIが作ったから」「知らなかった」という言い訳は、残念ながら通用しません。
2. ブログの信頼性を破壊する「ハルシネーション(誤情報)」
AIは時として、事実に基づかない情報(例:架空の統計データ、存在しない法律、誤った医療情報)を、さも真実であるかのように非常に流暢に、自信満々に生成します。これが「ハルシネーション(虚偽)」です。
もし、あなたのブログが発信した誤情報を読者が信じ、行動に移した結果、何らかの損害を被ってしまったら…? あなたのブログが長年かけて築き上げてきた「信頼性(Trust)」は、その一記事によって一瞬で失墜します。
「炎上」はすでに対岸の火事ではない
これらのリスクは、もはや「遠い未来の話」や「他人事」ではありません。
海外では、ニューヨーク・タイムズのような大手メディアや著名な作家たちが、AI開発企業を相手取り「著作権侵害」で相次いで訴訟を起こしています。
世界に目を向ければ、EU(欧州連合)で「EU AI法」という包括的なAI規制法が成立するなど、法整備が急ピッチで進んでいます。
日本国内でも、各企業がAI利用に関するガイドラインの策定を急いでおり、AIが生成したコンテンツへの「法的・倫理的な目」は、日増に厳しくなっています。
AIを「全自動の記事作成機」として丸投げする時代は、終わりました。
本記事の目的は、AIブログ運営者が直面するこれらの法的・倫理的リスクを正しく理解し、炎上を未然に防ぐための「実用的なセルフチェックリスト」を手に入れてもらうことです。
AIは「暴走する道具」ではありません。リスクを正しく管理すれば、あなたのブログ運営を加速させる「最強のパートナー」となります。
この記事を最後まで読み、AIを「安全に」使いこなす術を身につけ、読者から真に信頼されるブログを育てていきましょう。
※なお、本記事はAIブログ運営者が知っておくべき倫理的・実務的リスクと対策をまとめたものであり、法的な助言を行うものではありません。法的な判断については、必ず専門家にご相談ください。
第1章:「知らなかった」では済まされない。AIブログ最大の法的リスク「著作権侵害」
導入セクションで「AIブログの時限爆弾」という話をしました。本章では、その一つ目にして最大の法的リスクである「著作権侵害」について、深く掘り下げます。
なぜAIを使うと著作権を侵害してしまうのか? 万が一、侵害してしまったら誰が責任を負うのか? そして、法的には何が「アウト」とされるのか?
AIブログ運営者として、絶対に知っておかなければならない「守りの知識」です。
私が体験した「AIデッドコピー」の恐怖
本題に入る前に、少しだけ私の「ヒヤリハット体験」(E-E-A-T: Experience)をお話しさせてください。
このブログ(prompter-note.com)の記事執筆でAIを活用していた時のことです。あるニッチな技術解説のセクションをAIに生成させ、その草案をいつものようにチェックしていました。その日は少し急いでいたのですが、「念のため」と、生成された文章の一節をコピーしてGoogle検索にかけました。
その瞬間、血の気が引きました。
検索結果のトップに表示されたのは、とある個人の技術ブログ。そして、そこには私がAIから受け取った文章とほぼ同一のパラグラフが存在していたのです。
AIは、学習元となった(であろう)そのブログ記事の表現を、ほとんどそのまま「デッドコピー」として吐き出していたのです。
もし、私がそのチェックを怠り、「AIが作ったからオリジナルだろう」と高を括ってそのまま公開していたら? 間違いなく私は「著作権侵害」の加害者になっていました。AIというブラックボックスが、私を「盗作者」にしてしまう一歩手前だったのです。
なぜAIは「盗作」してしまうのか?
この体験から学ぶべきは、「AIは意図せず盗作してしまう」というメカニズムです。
多くの人が「AIはゼロから文章を”創作”している」と誤解していますが、実態は「学習データに基づいて、次に続く確率が最も高い単語を”予測”し、連結させている」に過ぎません。
AIは、インターネット上の膨大な記事、ブログ、書籍、ニュースサイトを学習しています。
もし、AIがある特定のトピックについて、非常に質の高いAという記事を「主食」のように学習していたらどうなるでしょう?
AIにとって、そのトピックの「正解」はAという記事の文体や表現そのものになります。
結果、私たちが「〇〇について書いて」と指示を出すと、AIは「はい、これが最も確率の高い(Aという記事にそっくりな)文章です」と、悪意なくデッドコピーを生成してしまうのです。
責任の所在は「AI」ではなく「あなた」
ここで最も重要な法的原則をお伝えします。
もしAIが生成した記事が著作権を侵害していた場合、その法的責任を負うのは、AI開発企業でも、AIそのものでもありません。
その記事を自身のブログに「公開」した、運営者である「あなた」です。
「AIが勝手にやった」「学習データに問題があった」「私は元ネタの存在を知らなかった」
こうした主張は、法廷では通用しません。
現に、海外ではAIの学習データや生成物をめぐり、Getty Imagesやニューヨーク・タイムズ、著名な作家たちがAI企業を相手取って大規模な訴訟を起こしています。
これは、AIの「生成・利用」がいかに法的に危険な領域にあるかを示しています。私たちブロガーは、この「法的な戦場」の最前線に立たされているという自覚を持たなければなりません。
【超重要】侵害を判断する「2つのモノサシ」
では、法的には何をもって「著作権侵害」と判断されるのでしょうか?
これは非常に専門的な分野ですが、AIブログ運営者としては、最低限「2つのモノサシ」を理解しておく必要があります。
日本の裁判所が著作権侵害(特に複製権・翻案権の侵害)を判断する際、主に以下の2つの要件が揃っているかを見ます。
- 類似性(るいじせい):あなたのAI生成物が、既存のAという著作物と「似ている」こと。
- 依拠性(いきょせい):あなたが、既存のAという著作物を「知った上で、それに基づいて」AI生成物を作ったこと。
この2つが揃って初めて「侵害」と認定されます。
1. 類似性(似ていること)
これは比較的わかりやすいでしょう。AIが生成した文章が、他人のブログ記事と「丸パクリ」や「デッドコピー」状態であれば、当然「類似性あり」と判断されます。
注意点は、単語をいくつか変えただけのリライト(いわゆる「てにをは」を変えただけ)でも、表現の本質的な部分が共通していれば「類似性あり」と見なされることです。
2. 依拠性(元ネタを知って利用したこと)
ここが、AIブログ運営における最大の落とし穴であり、最も議論が白熱している法的論点です(E-E-A-T: Expertise)。
「依拠性」とは、簡単に言えば「元ネタにアクセスして、それを真似した」という事実です。
ここで、多くのAIブロガーが陥る「危険な誤解」があります。
「私は元ネタのブログなんて読んだこともない。AIが勝手に作っただけだ。だから私には『依拠性』はないはずだ!」
この主張は、残念ながら非常に危険です。
確かに、あなた自身は元ネタにアクセスしていないかもしれません。しかし、あなたが「道具」として使ったAIは、学習の過程で元ネタにアクセスしている可能性が極めて高いのです。
弁護士や法律専門家の間では、「AI利用者が学習データを具体的に認識していなくても、AIを介して間接的に元ネタにアクセスしている(依拠している)」と判断されるリスクが強く指摘されています。
裁判所が、AIが生成した文章と元ネタの類似性があまりに高い(「デッドコピー」レベル)と判断した場合、「これは依拠していなければ、これほど似るはずがない」と、経験則から「依拠性」を推定する可能性があります。
つまり、「知らなかった」という言い訳は、「依拠性はない」という法的な反論にはならない可能性が高いのです。
日本の「AIと著作権」ルールを正しく理解する
では、日本の法律(著作権法)はAIをどう扱っているのでしょうか?
これについては、文化庁が「AIと著作権に関する考え方について」というガイドラインを公表しており、これが現在の日本の基本的なスタンスとなっています。
ここで、AIブロガーが絶対に混同してはいけない「2つの段階」があります。
段階①:AIの「学習段階」
AIがインターネット上の著作物を集めて「勉強」する段階です。
日本の著作権法第30条の4は、この「情報解析(AIの学習など)」を目的とする場合、原則として著作権者の許諾なく著作物を利用できると定めています。
これは、AI開発企業を保護する(AI開発を促進する)ための法律です。
段階②:AIの「生成・利用段階」
AIが学習を終え、私たちが実際にAIを使って記事を「生成」し、ブログに「公開(利用)」する段階です。
私たちAIブロガーがいるのは、この段階です。
そして、この「生成・利用段階」は、著作権法第30条の4の保護対象外です。
つまり、AIの学習が適法だったとしても、その結果としてAIが生成したアウトプットが、既存の著作物と「類似」し「依拠」していれば、それは通常の著作権侵害として扱われるのです。
これが、AIブログ運営における法的リスクの核心です(E-E-A-T: Expertise)。
- AI開発者(学習段階):法律(30条の4)で守られている(ことが多い)。
- AI利用者(利用段階):法律で守られていない。生成物の全責任を負う。
AIが生成したデッドコピーは、いわば「AIが学習段階で飲み込んだ他人の著作物を、そのまま吐き出した」ようなもの。それを受け取って「公開」ボタンを押す私たち利用者が、全責任を負うことになるのです。
この深刻な「法的リスク」を理解した上で、次章では、もう一つの「時限爆弾」であり、ブログの「信頼性(Trust)」を根底から破壊する「ハルシネーション(誤情報)」の罠について見ていきましょう。
第2章:信頼を失う「ハルシネーション(誤情報)」の罠と倫理的責任
前章では、他者の権利を侵害する「法的リスク」としての著作権侵害について解説しました。それは主に、私たちブロガーが「加害者」になるリスクでした。
しかし、本章で扱う「ハルシネーション(Hallucination=虚偽、誤情報)」は、性質が全く異なります。
これは、AIが生成する「ウソ」によって、あなたの読者が「被害者」になるリスクであり、ブログ運営の根幹である「信頼性(Trust)」を、再起不能なレベルまで破壊する倫理的な罠です。
ハルシネーションとは何か? なぜ「最強の詐欺師」と呼ばれるのか
ハルシネーションとは、AIが事実に基づかない情報を、あたかも真実であるかのように、非常に流暢かつ自信満々に生成する現象を指します。
多くの初心者が、「AIはスーパーコンピューターだから、常に正しい答えを知っている」と誤解しています。これは致命的な間違いです。
ここで、AIブログ運営者として、あなたの「AI観」を根本から変える(E-E-A-T: Expertise)必要があります。
- 間違った認識:AI = 事実を知っている「超優秀な図書館司書」
- 正しい認識:AI = 図書館の全ての本を丸暗記したが、一行も理解していない「口だけが達者な新人」
AIの根本的な仕組みは、「事実」を検索することではありません。学習したデータに基づき、「統計的に、次にこの単語が来たら最も”それらしい”」という確率予測で文章を生成しているだけです。
AIは「真実かどうか」には一切興味がありません。「流暢かどうか」だけが全てです。(その「新人」は、上司(=ユーザー)に「知りません」と答えて評価を下げるのを恐れ、記憶の断片(学習データ)をそれらしく繋ぎ合わせて、最も「もっともらしい」報告をでっち上げてしまうのです)。
だからこそ、AIは「情報がない場合」や「知らないこと」を聞かれても、「知りません」とは言いません。その場で最も”それらしい”ウソを堂々と作り上げてしまうのです。
実際に起きている「ハルシネーション」の恐ろしい事例
これらは、実際に世界中で報告されているハルシネーションの典型例です。
- 医療・健康ブログ:
「(架空の)最新研究によると、〇〇(存在しないサプリ)が効果的です」と、誤った医療情報や治療法を生成する。 - 法律・金融ブログ:
「(存在しない)〇〇法によれば、〜」と、架空の法律や判例を引用する。米国の弁護士がAIの生成した「偽の判例」を裁判所に提出し、大問題となったのは有名な話です。 - レビューブログ:
「〇〇(実在しない商品)は、最高の〜」と、架空の製品や存在しない人物の経歴を詳細にレビューする。 - 技術ブログ:
「(存在しない)論文によれば〜」と、架空の出典や統計データを引用する。
AIは、これらのウソを「〜かもしれません」「〜のようです」といった曖ym な表現ではなく、「〜です」「〜とされています」と断定的に生成するため、見抜くのが非常に困難なのです。
これらすべての事例に共通するのは、単に読者の「信頼」を裏切るだけでなく、Googleが最も重視するE-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)を著しく毀損する行為であるという点です。特に医療や金融に関する誤情報は「YMYL(Your Money Your Life)」領域に直結し、ブログ運営者として最も回避すべき、読者の人生を危険に晒す行為となります。
なぜこれは「法的責任」以上に「倫理的責任」なのか
前章の「著作権侵害」は、他者のコンテンツを盗む「加害行為」でした。
しかし「ハルシネーション」は、あなたのブログを信頼して訪れた読者に、積極的に「毒」を盛る行為に他なりません。
考えてみてください。
もし、あなたのブログがAIの生成した「デタラメな健康情報」をそのまま掲載し、それを信じた読者が健康を害したら?
もし、あなたのブログがAIの生成した「デタラメな法律情報」を掲載し、それを信じた読者が金銭的な損害を被ったら?
その時、あなたは「AIが作ったので知りません」という言い訳ができますか?
法的な責任を問われるかはケースバイケースかもしれませんが、あなたのブログが読者から「信頼できる情報源」として見られることは、二度とないでしょう。
これは、Googleが検索品質の核に据える「E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)」の、特に「信頼性(Trust)」を根底から否定する行為です。
AIの出力を検証せずに公開することは、読者の安全を軽視しているとGoogleに判断され、ブログ全体の評価を致命的に下げる原因となります。
AIの効率化は魅力的ですが、その効率化によって「読者を危険に晒す」のであれば、それはもはや「運営術」ではなく「怠慢」です。
AIブログ運営者には、その生成物に「最終的な責任を持つ」という重い倫理的責任が課せられているのです。
第3章:炎上を未然に防ぐ!「AIブログ運営者」のための法的・倫理的セルフチェックリスト
第1章(著作権侵害)と第2章(ハルシネーション)で、AIブログ運営に潜む「法的リスク」と「倫理的リスク」を解説しました。
「AIって、やっぱり怖い」「リスクが多すぎて使えない」…もしあなたが今、そう感じているとしたら、それは正常な感覚です。リスクを知らないままAIに「丸投げ」していた時よりも、あなたは確実に安全なブロガーに近づいています。
知識(第1章・第2章)は、恐怖を煽るためにあるのではありません。リスクを「管理」するためにあります。知識だけでは炎上は防げません。炎上を防ぐのは「行動」であり「仕組み」です。
本章は、この記事の核心です。
私が実際に「AIデッドコピー」の恐怖(E-E-A-T: Experience)を体験して以来、記事公開前に必ず実行している「炎上回避セルフチェックリスト」を、惜しみなく公開します。
AIを「危険な暴走車」から「安全な副操縦士」に変えるための、具体的な手順書です。
その手順の「土台」となる、最も重要な心構えから始めましょう。
チェックリスト1:【マインドセット】の最終確認 (最重要)
具体的な「手法(How)」の前に、最も重要な「心構え(Why)」をチェックします。このマインドセットがなければ、面倒な著作権チェックやファクトチェックは「どうせバレないだろう」と省略され、炎上への道を歩むことになります。
✅ 1-1:AIを「著者」ではなく「アシスタント」として扱っているか?
- 私のアドバイス (E-E-A-T: Expertise):
- (NG)AIに「記事を書かせる」。あなたは「公開ボタンを押す人」。
- (OK)AIに「リサーチと草案作成を手伝わせる」。あなたは、その草案を「検証」「編集」「追記」し、最終的な品質に全責任をを持つ「編集長(Editor-in-Chief)」である。
✅ 1-2:AI利用を明記し、読者への「誠実性」を担保しているか?
- 私のアドバイス (E-E-A-T: Trust): AIが生成したかもしれない(あるいは支援を受けた)コンテンツであることを、免責事項として明記する文化が広まっています。
- これは「この記事はAIが書いたので、間違っていても責任を取りません」という「免責」のためではありません。
- 「この記事は、読者の皆様により良い情報を届けるため、AIの支援を受けていますが、最終的な編集・検証は私(運営者)が責任を持って行っています」という「読者への誠実な姿勢」を示すために行う、E-E-A-T(信頼性)の担保です。
この「編集長」としてのマインドセットが固まって初めて、次の具体的な「道具(ツール)」を使う意味が生まれます。
チェックリスト2:【著作権侵害】対策(公開前の”防御”)
「編集長」として、アシスタント(AI)が持ってきた草案が、他者の権利を侵害していないか(第1章のリスク)をチェックします。
✅ 2-1:AI草案を「コピペチェックツール」にかける
- なぜ?: AIが学習元と酷似した表現(デッドコピー)を吐き出していないか、機械的に確認するためです。
- 方法: 生成された文章(特に「上手く書けすぎている」と感じる部分)を、無料または有料のコピペチェックツール(例:CopyContentDetectorなど)にかけ、類似率が高くないかを確認します。
- 私のアドバイス (E-E-A-T: Expertise): 類似率が「0%」になるまで修正する必要はありませんが、特定のサイトと「文章単位」で一致(デッドコピー)している箇所が見つかった場合、それは即時修正(リライト)が必要です。(これは、第1章でお話しした、私が『デッドコピー』を発見して冷や汗をかいた、まさにその『防衛線』です)
✅ 2-2:「てにをは」ではなく「構造」をリライトする
- なぜ?: 第1章の「依拠性」を断ち切り、あなたの「創造性(オリジナリティ)」を記事に加えるためです。
- 方法:
- (NG)「私はAIを使います」→「私はAIを利用します」(単語の置換)
- (OK)「AIが生成した文章」→「AIが吐き出した草案を、私自身の言葉で再構築し直し…」(構造と意味の再構築)
- 私のアドバイス (E-E-A-T: Expertise): AIの草案は、あくまで「素材」です。その素材に、あなたの「体験談(Experience)」、あなたの「独自の分析(Expertise)」、あなたの「文体(声)」を加えて初めて、それは「あなたの記事」になります。AIの文章を6割以上書き換えるつもりで向き合うのが、最も安全な著作権対策です。(具体的なリライトや検証のフローについては、別記事の「AIブログ丸投げで大失敗した私が辿り着いた「プロ品質」 11工程ワークフロー」でも詳しく解説しています)
チェックリスト3:【ハルシネーション】対策(公開前の”検証”)
「編集長」として、アシスタント(AI)が持ってきた草案に「ウソ」が混入していないか(第2章のリスク)をファクトチェックします。
✅ 3-1:全ての「固有名詞」と「数値」を疑う
- なぜ?: AIは、第2章で述べたように「それらしいウソ」の数字や名前を平気で作り出すためです。
- 方法: 記事に含まれる以下の要素は、「全てウソかもしれない」という前提で、必ずGoogle検索や公的機関のサイト(一次情報)で裏付けを取ります。
- 統計データ(例:「日本のAI市場は2030年に〇〇兆円…」)
- 法律名、判例、公的文書
- 人名、企業名、商品名
- 歴史的な年号、出来事
- 引用文(「〇〇はこう言った…」)
- 私のアドバイス (E-E-A-T: Expertise): ファクトチェックは「AIにやらせ」てはいけません。AIに「この情報合ってる?」と聞いても、AIは平気でウソの裏付けをします。必ず「あなた自身の目と手」で、AIが提示した出典(ソース)が実在するか、信頼できる情報源(一次情報)かを検証してください。
✅ 3-2:プロンプトで「AIの行動」を制限する(上級テク)
- なぜ?: AIに「自由に」書かせると、ハルシネーションのリスクが高まります。
- 方法 (1) RAG(検索拡張生成):
- (NG)「〇〇について教えて」
- (OK)「以下のURL(信頼できる一次情報)だけを参考にして、〇〇について解説して」
- 方法 (2) Temperature設定:
- もしあなたが使っているAIツールで「Temperature(温度)」というパラメータをいじれるなら、値を「0」に近づけてください(例:0.1〜0.3)。
- Temperatureが高い=創造的・ランダム(ウソをつきやすい)
- Temperatureが低い=保守的・安定的(事実に忠実になりやすい)
- 方法 (3) 不明時の指示:
- プロンプトの最後に「情報が不明な場合、または事実確認が取れない場合は『不明です』と回答してください」という一文を必ず加えます。
- (こうしたAIの出力を制御する具体的な指示(プロンプト)技術については、「AI記事の品質革命。検査プロンプト術」でも詳細を解説しているので、併せてお読みください。)
このチェックリストを実践することは、「AI自動化」という甘美な響きとは裏腹に、非常に手間がかかります。
しかし、この「手間」こそが、あなたのブログを法的・倫理的リスクから守り、Googleと読者の両方から「信頼」される唯一の道なのです。
[提案] このチェックリストは、AIブログ運営の「お守り」になります。ぜひブックマークするか、記事公開前の「指差し確認」としてご活用ください。([図解:AI炎上回避セルフチェックリスト]やダウンロード可能なPDFを末尾に用意するのも良いでしょう)
まとめ:リスク管理こそがAIブログ成功の鍵
AIブログ運営の「成功」とは、単に記事を量産することではありません。
本記事で見てきたように、AIの力を無防備に信じ「丸投げ」することは、「著作権侵害」(第1章)と「ハルシネーション」(第2章)という2つの時限爆弾を抱えることと同じです。それは効率化ではなく、読者と自身の信頼を失う「怠慢」です。
本当の「AIブログ運営術」とは、AIを「著者」にするのではなく、あなたが「編集長(Editor-in-Chief)」としてAIを「安全な副操縦士」に据えることに尽きます。
第3章で提示した「セルフチェックリスト」の実践は、正直に言って「手間」がかかります。しかし、その「手間」こそが、あなたのブログを法的・倫理的リスクから守り、読者からの「信頼(Trust)」を獲得し、E-E-A-Tを高める唯一の道です。
AIの効率性(Speed)と、あなたの編集者としての責任(Trust)を両立させる。
それこそが、AI時代を生き抜くブロガーの姿であり、Googleと読者の両方から「E-E-A-T(特に信頼性)」が高いと評価され、他のAI量産ブログとは一線を画す「本物の」情報発信者として長期的に成長するブログ運営の鍵です。
まずは第3章の「セルフチェックリスト」をブックマークし、次回の記事執筆から、あなたも「編集長」としての一歩を踏み出しましょう。
P.S. 本記事では私の「ヒヤリハット体験」をお話ししましたが、ぜひコメント欄で、あなたの「AIヒヤリSット体験」や「独自のチェック術」も教えてください。一緒にE-E-A-Tの高いブログ運営を目指しましょう。
おすすめ関連記事
この記事で解説したリスク管理やAIの活用法について、さらに深く知りたい方のために、以下の記事もおすすめです。
- AIブログ自動化の心臓部! 変数を制して品質を操る技術 – チェックリストで触れたAI制御の、さらに進んだテクニックです。
- AIブログ自動化 最適解ガイド – 「編集長」としてAI自動化ワークフローを組むための全体像を解説しています。
- AI精度劇的UP! Markdown プロンプト術 – AIへの指示(プロンプト)の精度を上げるための実用的なテクニックです。


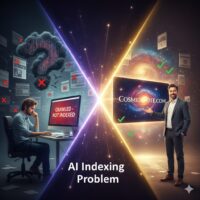





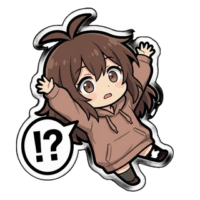



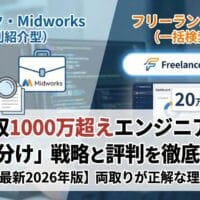

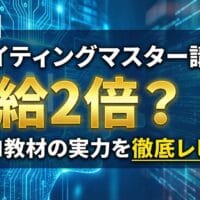

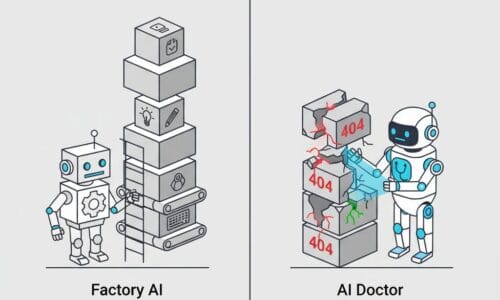

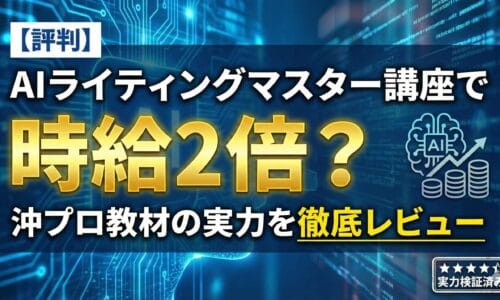


この記事へのコメントはありません。